はじめに

3Dプリンターのイメージは「ボタン押せばあとは勝手に・・・」というように思う方が殆どだと思います。
実は・・弊社で使用する金属3Dプリンターも、そしてその他の金属3Dプリンターでも実際には造形途中で停止します。
出来れば停止して欲しくないのですが・・それはまだ叶わない夢でして・・何らかのトラブルで停まります。
トラブルが起きれば造形の失敗確率はグンとあがります。
また自身がどれくらいの大きさまで造形できるのかを知ることが大事です。
お問い合わせはこちらから
失敗事例

まず造形失敗の主な原因となるトラブルをみてみましょう。
トラブル原因
1.造形品の膨張(歪み)
2.造形品の角部のめくれ
3.ヒュームのひっかかり
4.酸素濃度上昇(センサーの破損)
5.地震
などがあげられます。
上位3っの停止が一番多いのですが、様々な要因で停止します。
セミナーや講演等では金属3Dプリンターの失敗事例を交えてお話をさせて頂いておりますが、停止してから早い復旧が望まれます。
早い復旧ができない場合、場合によっては初めから造形のやりなおしという場合もあります。
素早い復旧をしなかった場合、どのような失敗が起こるかといいますと、造形割れです。特に大きなものを造形する際に発生確率があがってきます。
次に管理体制による失敗です。
なんの管理体制かといいますと、金属粉末になります。
保管してある金属粉末に湿度が多く含まれてしまったり、酸化が進んでいたり、フルイ(リサイクルの為の)にかけてなかったりすると造形不良の原因となります。
まず湿度からお話をしますと、金属粉末に湿度が含まれてしまった場合粉末の流動性が著しく悪くなります。それにより粉末を均一に敷き詰められなくなり密度の低下を招きます。また、湿度がはいったまま造形そすると水分がレーザーの熱により酸素と水素に分離します。そして積層工程の過程で金属内に入った水素は、応力下で拡散し金属を脆くします。そして最終的に応力が加わっているので割れを生じます。
また巣のような現象になることも確認できています。湿度の管理は徹底して造形することが大事になります。
失敗事例の中で多い順に並べてみると
1.造形割れ
2.歪み大
3.崩れ
となっています。圧倒的に多いのが造形割れですが先ほど説明した原因によっておこる現象です。
応力も常に発生していますので、うっかりすると割れが出てしまいます。
次の歪みですが、造形はできたが基準プレートから切り離した後に歪みが発生する現象です。社内にてアニール処理はしておりますが、残念ながら形状によっては歪みが大きくなる場合があります。
思ったより発生しないのが崩れです。
崩れに関してはやはりノウハウによるところが大きく、サポート設計や造形姿勢によります。
またこれは金属3Dプリンターの種類によっても差がありますので、すべてのメーカーの金属3Dプリンターで同じ現象が出るわけではありませんので、独自のノウハウを積み重ねる必要があります。
お問い合わせはこちらから
まとめ
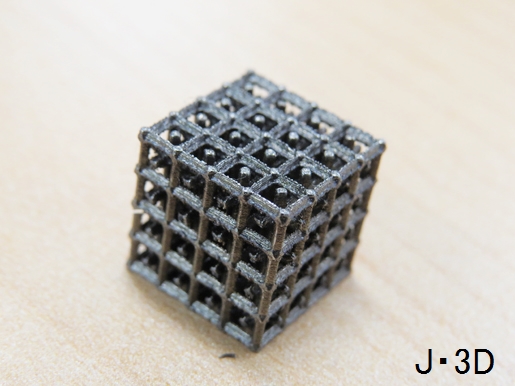
金属3Dプリンターはその工法のプロセスからして応力の発生とは切り離すことが出来ません。
弊社もそうですが、この応力に対する考え方を克服しなければノウハウが蓄積できないのです。
お客様に商品として提供する以上、多くのノウハウを積み重ね良品を提供する事が私たちの努めでもあります。
これから事業を始めよう、また、今から金属3Dプリンターを購入する企業様にも言えることですが、ノウハウをためるためにはあらゆる形状にチャレンジし、その結果を常にフィードバックしなければなりません。
「失敗は成功のもと」と言いますが、まさにそれを実践しつつ金属3Dプリンターの技術の取得に努めていきましょう!
お問い合わせはこちらから






